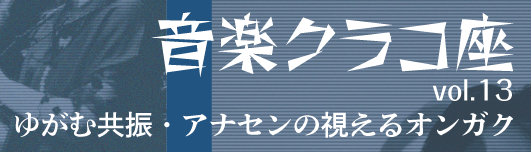Studies for String Instrument(弦楽器のための習作)は#1から#3までの3曲あります。共通するのは作曲者自身がこの解説の冒頭に「Movement of the sound or sound of the movement?」(音の動きか、動きの音か?)と書いていることです。
この場合の「Movement」とは奏者の動きであり、それは通常、音を出すための挙動ということになります。音を出す際の奏者の挙動に焦点を当てた作曲家としては、M.カーゲル(1931-2008)が思い浮かびます。彼は音を出すための身体の動きを「ミュージック・シアター」というスタイルに落とし込みます。それまで意識化では誰もが気づいていた、音を出すための必要行為に過ぎなかった身体の動きに着目し、その視覚的効果を演劇的な舞台に引き上げたという言い方ができます。
アナセンは(他の作品にも共通していえることですが)身体の動きを、出てくる音と対等に、いやそれ以上のものとして意識的に扱います。解説は続きます。「一つのシンプルな動きはくり返され、個々の要素にゆっくりと分解され、曲は動きとしてのみ記譜される」。その結果、この作品の記譜は、出てくる音が目的というよりも、もはやそれは「振り付け」であり、「ダンス」であるということです。
その視点から書かれた3曲は次のようなものです。
#1はソロ楽器のために書かれていますが、複数人でユニゾンで演奏しても良く、弦楽器以外の楽器が加わっても良いとのことです。
今回の公演では、もっともピュアな「原曲」をお聞きいただくため、ヴァイオリンのソロで演奏します。
#2はソロ楽器の音をマイクで拾い、アシスタントによる「ワーミーペダル」を通します。ワーミーペダルは入力された電気信号のピッチを変化させます。舞台上では元の楽器の音とワーミーペダルによって変調された音が同時に鳴り、リスナーにはどちらもその挙動が見えるため、「演奏と変調」の結果が視覚と聴覚で確認できることになります。
たとえば弦楽器は通常、左手が指板を動くことによって音高が変わりますが、その手を動かさなくても隣のワーミーペダルによって音が変わる、という「奇妙」なことが実現されます。ここにアナセンが狙う「視覚と聴覚のズレ」が生じます。
#3はもっと大がかりです。楽器はチェロが指定されます。奏者は二人羽織のように、事前に撮影された動画と生演奏が重なります。このとき「二人」は、最初はユニゾンで同じ動きをしますが、少しずつズレていき、やがて瓦解していきます。
余談ですが、#3は特に楽器そのものに対する要求が高く、最低弦をさらにオクターヴ低く調弦し、布きれとマスキングテープを付ける指示があります。単に視覚と聴覚をずらすだけではなく、聞こえてくる音も「非・楽音」であるため、もはや弦楽器を使った何か違う楽器を演出しているようにさえ思わされます。
音楽クラコ座vol.13「ゆがむ共振・アナセンの視えるオンガク」のお申し込みはこちら!
Peatix▶https://qulacoza13.peatix.com/
音楽クラコ座公式サイト▶https://qulacoza.net/?page_id=254
プレイガイド▶愛知芸術文化センタープレイガイド052-972-0430
※平日10:00-19:00、土日休日10:00-18:00、月曜定休(祝日の場合は火曜休)