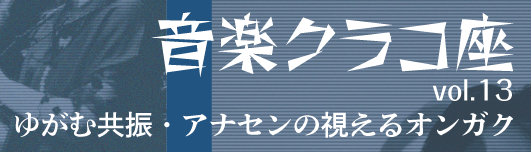邦題は「実現への険しき道」と訳してみました。この曲を体現しています。アナセンの曲はどれも難しいのですが、ここには他と違った困難さがあります。
楽器を使わないのです。
楽器を使わないで、いわゆる身の回りのものを使う、そしてその道具などを扱う挙動を音にする、というところはFrancesco Filideiとの共通性も感じます。ただそれはあくまでも表面的な部分で、アナセンのこの曲ではより徹底的であり、しかも「エア・ギロ」とかいう楽器も作らせます。これは紙に櫛状の穴を開けたもので、スコアにはわざわざ型紙が印刷されています。
Studies for String InstrumentやNext to Beside Besidesでは、奏者の挙動に即して出てくる音がズレたり歪んだりする、という話は前の記事で書きましたか、Difficulties Putting It into Practiceでは意外にそういう場面はありません。奏者の挙動は小さく、エア・ギロに吹きかける息、口からでる声やノイズ、紙にペンで擦る音、紙を破る音などは、すべて増幅されなければ聴衆に届きません。机の上で二人の奏者(演者?)が発する音は、虫眼鏡で見るようにマイクを通して聴き手に届けられます。
アナセンはこれらの音をミュージックコンクレートのように音があるがままに提示するのではなく、かなりリズミカルにわかりやすく「加工」します。それによってこれらの音は容易に従来の(旧来の、といっても良い)「楽音」として認識されるでしょう。その楽音の組み立て方、音楽の作り方はわかりやすく古典的ともいえます。
ただ楽器を使わない、だけです。
楽器を使わないというのは、演奏者にとっては「新しい楽器」を使え、といわれているのと同じです。前述のように様々な音は明確に「楽音」として聞こえなければならないため、紙やペンなど通常は楽器として用いられないものを明瞭に「発音」させる必要があります。そうしなければリズムも曖昧になってしまいます。これは楽器でないものを楽器に変換する作業です。とても音楽的な楽曲を、音楽的でない手段を用いて実現する「険しき道」であり、観客はそれを見届けなければなりません。